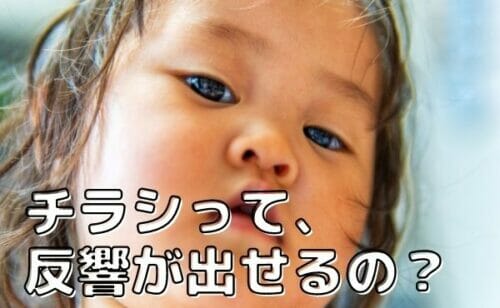こんにちは!
医療情報ポータルサイト「ドクターズ・ファイル」の鳥取島根エリアの編集担当の佐々木です。
前回は「意外と知らない?最近よく聞く“かかりつけ医”について」というテーマで、
コロナ渦でよく聞くようになった ”かかりつけ医” について
私が「ドクターズ・ファイル」の取材や制作を通して学んだことを紹介させていただきました。
そして、今回はそのかかりつけ医の ”地域の中の役割” というテーマで
かかりつけ医を始めとした地域の医療機関のそれぞれの役割と、その上手な活用方法について
実際にクリニックの先生を取材させていただいて感じたことも含めてお話しさせていただければと思います!
病院とクリニックの違いって知っていますか?
皆さんは、医療機関は主に ”病院” と ”クリニック” にわかれるということをご存知でしょうか?

病院の定義は、複数の診療科があって20以上の病床を持つ医療機関のことを指すそうです。
道を歩いている時に「大きい病院だな」と感じるような、例えば、建物が2・3階以上あったり、平屋だけどとても広かったりするものは 定義上も”病院” であることは多いかもですね。

対して、クリニックの定義は、19以下の病床を持つか、もしくは病床がない ”診療所” のことを指すそう。
また、”診療所” の中には、クリニックのほか、名前に、”医院” や ○○科(内科・眼科・皮膚科・耳鼻科や歯科 等) がつく医療機関も含まれます。
”病院” と ”クリニック”(正しくは病院と診療所かもですね 汗)は名前が違うように、その役割も違います。
それぞれの役割とは
まず、病院にはどんな役割があるでしょうか?
それは病院の定義に「病床数の多さ」を挙げた通り、入院も想定されるような重症疾患を主に対応します。
”重症疾患” というと難しく聞こえますが「急に発症して重症化するような症状」といったイメージです!
ほかには、CTやMRIなどの精密機器での検査が必要な場合も、病院を利用することが多いですね。
次にクリニックが担っている役割とは。
クリニックでは、軽いけがや病気、慢性的疾患を主に対応します。”慢性疾患” とは、手術や治療によって症状は落ち着いているけれど、継続して治療や経過の観察が必要な症状のことです。また、病院に重症疾患で入院していた人の症状が落ち着いたり、回復したりして退院した後を担当するのもクリニックの大切な役割です。
あと、これは「ドクターズ・ファイル」の取材をする中で初めて知ったのですが、クリニックによっては、研究や勤務経験から特定の分野への高い専門性を持った先生がいたり、それに合わせてクリニックに専門的な設備を揃えていたりする場合もあるので、気になる症状や受けたい検査がある方は、それが得意な先生を探したり、かかりつけ医に相談して紹介してもらうのもいいと思います!
それぞれの役割を理解して、目的によって使い分けをしましょう!
病院とクリニックの違いを簡単に説明させていただきました。
それでは、私たちは「どのように上手に使い分けしていけばいいのか」考えてみましょう!
主な使い分けは、大きくわけて以下の2つになるかと思います。
- 普段の身近な疾患はクリニックを利用しましょう
何か気になる症状があった場合は、まずはクリニックを受診しましょう。
精密検査が必要だったり、重症疾患の疑いがあったりする場合が、先生が適切な病院へ紹介してくれます。 - 急性期疾患が疑われる症状や緊急性のある症状がある場合はすぐに病院へ
「脳卒中」や「急性心筋梗塞」などの急性期疾患が疑われる症状や、「転倒で頭を強く打った」「突然ぐったりとして様子がおかしい」「熱中症」など緊急性のある症状がある場合は、すぐに病院へ行きましょう。
まずは、かかりつけ医へ相談しましょう
その人の状況に応じて、適切な医療機関にかかれるように手助けする存在が「かかりつけ医」です。なので、「何かおかしいな」と思ったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
私たちが正しく医療機関を利用することで、大きな病院に集中することが防げ、病院が本来の役割である高度な医療の提供に専念することができ、より多くの命を救うことに繋がります。
また、これも「ドクターズ・ファイル」の取材で教えていただいたことですが、
今後の地域医療のために、より広い症状を総合的に診られるように勉強をされたり、反対に自分の専門を磨かれたり、訪問診療を提供されたり、地域の病院・クリニックの連携を取られたりと、地域の「かかりつけ医」となるための様々な取り組みをされている先生もたくさんおられます。
ぜひ、ご自身にあった「かかりつけ医」を見つけて、正しい医療機関の利用をしていきましょう!





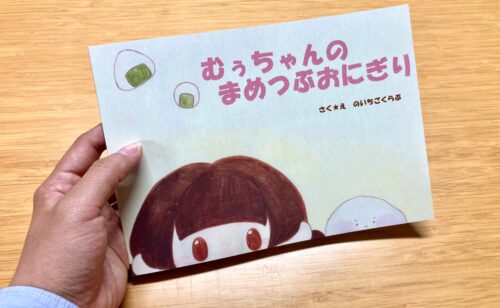

-500x308.png)